
北極星を指さす人、「飯を食わない」から始める
北極星を指さす人
髙野: では次の質問です。自分の問いから始める、というか、自分の内発的なものから始めていこうというのがCreative-LAB.にもASIBA全体にもあると思います。自分の問いが社会課題と結びついていくのってどういう風に結びついていくのでしょうか?
森原: 須藤に聞いてみたいですね。エンジニアリングで物を作りながら、社会運動とか思想とかも好きじゃないですか。そこがどう繋がっていると自分で思ってる?
須藤: かなり明確にあります。ラディカルに、と言っていいのか分かりませんが、新しいものを作りたいというのは、多分エンジニアもみんな持っているものだと思います。じゃあ本当に新しいものって何?と考えた時に、1つはコンセプチュアルアートでやっているような哲学など、めちゃくちゃ新しい概念を創出すること。もう1つは社会を巻き込んで新しいシステムをつくること。この2つが個人的にはめちゃくちゃ魅力的です。エンジニアでそういうことをやろうとしたら、多分やっぱりモノだけにとどまったら小さくなってしまうから、社会を巻き込んだ方がラディカルに面白いものが作れる、というイメージでやっています。森原とかがその近しいところに、近しいというか、先を行っているというかもしれない、実践をしている、というイメージですね。
あと、そもそもエンジニアみたいなデジタルなことをやっていると、デジタルなものしか作れないと思いがちですが、どうしても歴史とか調べたくなってしまうんです。70年代とかに情報社会学が生まれて、そこら辺を調べていると、やっぱり政治運動とか民主主義とかコミュニケーションとかと同じような話をしているんですよ。インターネットが出てきた最初の頃ですね。
髙野: 建築も似ていますよね。建築の方がもっと歴史が古いですけど。
森原: 社会課題が顕在化していない場所に「旗を立てる」のが、クリエイティブや建築の仕事だと私は思っています。建築家の永山裕子さんとかが「北極星を指差す人」だと言っているんですが、誰も空を見上げようと思わないと北極星は見つからないわけですよね。でも、そこが大事だよ、という人がいないと、多分その行動って始まらないはずで。そこって課題があるよって光っているものではなくて、「あっちの方がいいかも」とか「これの方が大事だよ」という指し方ができなければいけないと思っているんです。それは天から言われているものではありません。自分で見つけないといけなくて、その自分で見つけるには、それこそ自分なりに船を漕いでみたりとか、物を作りながらリアリティを自分に獲得していく中で「何を見なきゃいけないか」とか「これをやるためにはこの情報が必要なんだ」「このリサーチが必要なんだ」「この課題の理解が必要なんだ」「歴史の理解が必要なんだ」ということが分かった時に学びが始まるはずだし、つくることによって社会を認識するようになるはずだと思っているんです。
高野: 大事なのは実践を通じたラーニングですよね。それと、前半のポイントで言うと、つくることによって自分にしかない問いのようなものが見えてきて、それが社会でまだ言われていないからといって社会的でないわけではなく、むしろ課題が複雑化し、かつ多元化している現代において、いかに自分だけの問いを見つけ、それをアジェンダとして提示できるか、というのがクリエイティブの大きな役割だとASIBAは考えています。Creative-LAB.もそうですね。
森原: 強度の高い実践や物作りをするには、やはりベースの基礎や発想の仕方、物事の見方などが必要で、そこは飛ばしてはいけない部分です。物作りは非常に重量があって質量があるものなので、小手先では絶対にできませんし、バレてしまうようなものですからね。もちろん、実践を通して小手先ではできないと認識することも大事だと思いますし、その後に自分なりにラーニングして新しい学問に触れて深く学んでいくフェーズも大事です。逆に、例えばすごく座学をやってきたり本を読んできて、じゃあこれを社会に実装するにはどうしたらいいのか、というところから始まるような物作りという行為もきっとあると思います。Creative-LAB.がそのような経験ができる場所であればいいなと思いますね。
安全地帯を飛び出す
髙野: では次の質問です。安全地帯を出て、まだ誰にも見せていない100%で物を作ってみる、とステートメントに書いてありますが、皆さん自身、これまで安全地帯を飛び出した瞬間はありましたか?
僕は飛び出そうとしたことはありますね。大学受験で海外大学を受けていた時です。高1の時だったかな、高1の秋くらいに突然目覚めたんですよ。それまでは部活をずっとやって勉強して、を頑張っているような感じだったんですけど、たまたま高1の夏に高校でボストンに行くプログラムがあって、すごく高かったんですけど親に「ちゃんとこの分の価値を出しなさい」と言われて。そこに行ってすごく頑張って取り組んだ時に、今まで自分が過ごしてきた時間とかに対する疑念というか、「もっとやれたんじゃないか」とか「周りの人と感覚が合わないな」みたいな、スタンダードが一気に引き上がったような経験があって。私はすごく進学校にいたので、この中の1/5とか1/6が東大に行くのかと、当時の私はそういう成績とか大学みたいなところしか見えてなかったんですけど、その時に「いやでもそんなのやっても面白くないな」と思って。じゃあ海外に行こう、みたいなところが最初の踏ん切りとしてありました。
森原: なるほど。チャレンジをしたんですね。
高野: チャレンジはしていました。高1、高2、高3くらいはすごく頑張っていましたね。
森原: 受験だったら、私は海外の大学とかは全く考えていなかったんですけど、「大学なんて何のために行くんだろう」と本当に思っていました。なんで行かなきゃいけないんだろう、なんでこの人たちはみんな大学受験を目指しているんだろう、なんでみんな模試で一喜一憂しなきゃいけないんだろう、なんで隣の人とテストの点数を比べていかなきゃいけないんだろうと。そんなことで自分の価値を決められてたまるか、みたいなことを思って、私はもう受験勉強を辞めてしまったんですけど。受験クラスにいて40人中40位だったんですけど、それはもうずっと模試もサボり続け、テスト時間もずっと本を読み続け、というスタンスを取って、「こいつはダメだ」と言われていました。
その間もステルスでずっと絵を描いていて、デッサンを書き続けていました。家に帰ったり授業中とかも書き続けていて、それをポートフォリオにまとめて、たまたま早稲田に、成績とか関係なしに20人取る、みたいな制度があって。そこだけしか出していないんですけど、そこを出すこと、その意志を込めたのは、割と安全地帯を抜けるという1個目の行為だったなと思います。規定の路線を外れよう、となったというか。「いいや」みたいな。「俺は俺の人生で、俺は俺がこう自分でリスクを取って回収すればいいから、行けばいいんだ」と思ったのが、最初の安全地帯を飛び出してみた経験でしたね。その時に多分成功体験があるから、「まあなんとかなるだろう」と今もなんか別に就職しなくてもなんとかなるだろう、みたいなことを思ってしまっているのは確かにあると思います。強烈だったんだと思います、その時が。
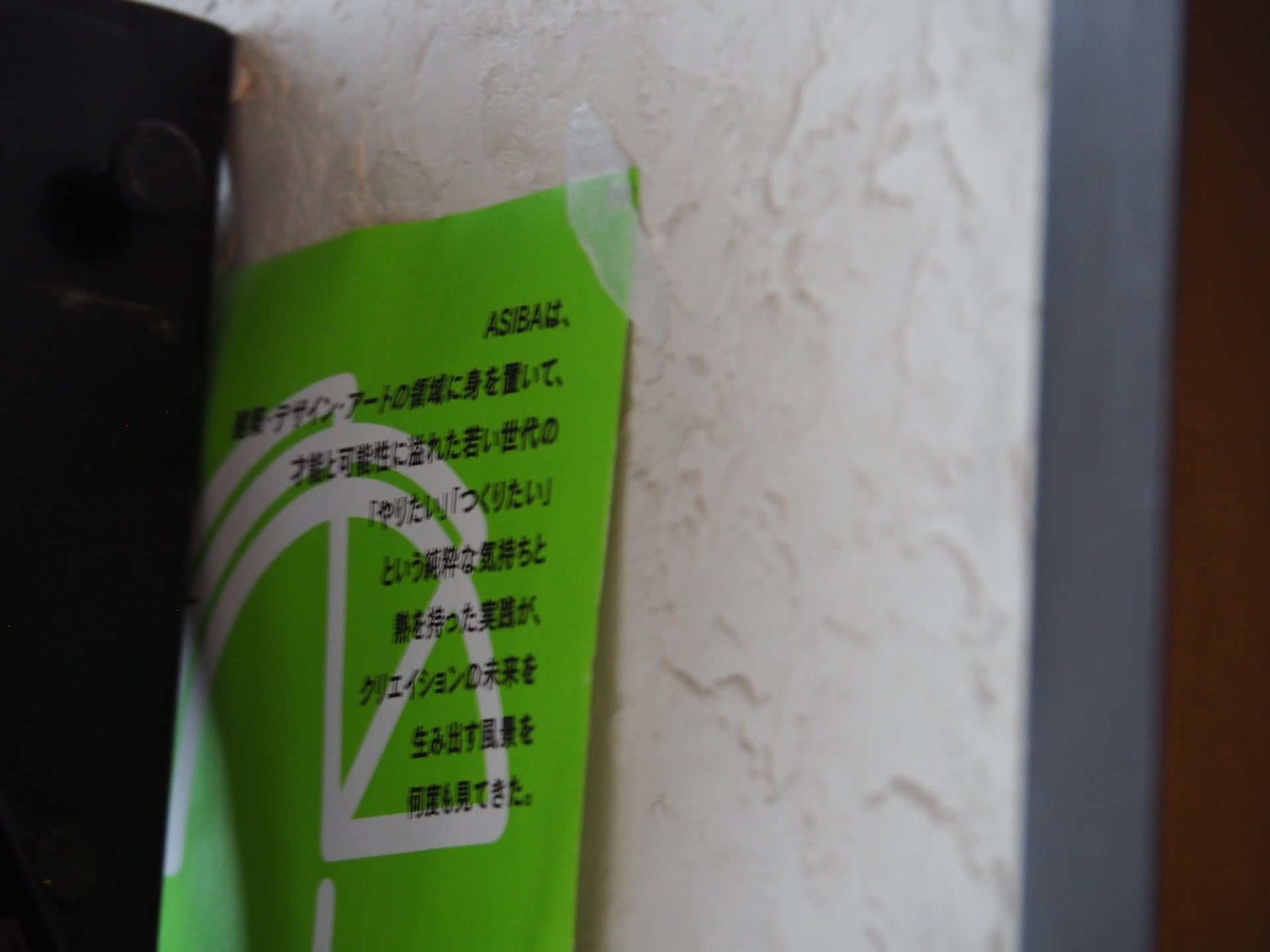
髙野: そうですね。私は逆に、メインストリームに乗ろうと思えばいくらでも乗れるという感覚が逆にあるから外れられるタイプかもしれません。
森原: 確かに、だいぶ違うね。完全に崖っぷちにいるからこそ「俺はつくるんだ」というポジションを獲得しているのかもしれない。
髙野: 全然違いますよね。僕はメインストリームにいながら自分のためだけに何かを作り続けるとか、生き続けることに対する恐怖や悪寒が強いです。なので、自分はそれでパブリックなことができるか分からないけれど、とりあえず外れるところから始める、という感じですね。
須藤: ちなみに私も似たような話があって、大学院の入試を当日にキャンセルしたことがあります。
森原: それやばいよ!なんで当日キャンセルしようと?当日までそれは行こうと思ったってことでしょ?
須藤: さっきの「何も考えてなかった」というのはそこまでです。その日から記憶があります。完全にモードが変わって、「なんで?」「このままでいいの?」となりました。やりたかった情報系が学部になかったというのが1つと、もう1つはもともと人文系を学びたかったけど、理系単科大学だから学べなかった、というのもあります。その前からキャンセルするかも、という頭はあったんですけど、ちゃんと勉強はしていたんですよ。先生にも「行きますよ」と言ったけど、当日で。
髙野: その当日何があったんですか?
須藤: やっぱり「違うな」とか「なんか違う気がする」という感じかな。
森原: でもやっぱりそういう、一旦ぬくぬくした場所から離れるというのは、色々な意味でいいことですね。全てが回り道から始まります。
髙野: 良い言葉ですね。僕の住んでいるシェアハウスは、冗談半分ですが「学年を落としたやつにしか入居資格ありません」と言っていて。最近はストレートが増えてきましたけど。もちろん、学年を落としたりできるのは経済的に恵まれているからできる、という大前提があるので、あまりそればかり打ち出すのは良くないなと思うんですけど、「何者でもない期間」に自分らしさが出てきますよね。
自分と言葉が通じない人と出会う
髙野: さて、次は、ラボとしてコミュニティとしてやることって、やっぱり人と人との化学反応とか、仲間がいることというのが、つくることや生き方を見つめることに対して大事だよね、という前提だと思うのですが、このラボでどんな化学反応が生まれてほしいかとか、これまで自分が化学反応的に変わったなという経験はありますか?
森原: 自分の経験か。化学反応。そうですね。それこそ「自分と言葉が通じない人と会う」というのは、良い化学反応のきっかけだなと。言葉が通じないというのは、日本語が通じないとか英語が通じないとかではなくて、論理構造が違うとか認識の構造が違うみたいなことです。圧倒的にマイノリティだ、頭の回路が違う!みたいな瞬間で、いかにその中で自分を自分だと言えるかどうか、みたいなところに化学反応が起きる瞬間があると思います。物質と物質が混じり合う瞬間なのかな。
だから、Creative-LAB.も同質性が高い場所にはあんまりしたくないなと思っています。無料だからこそ、色々なバックグラウンドを持っている人、色々な考えを持っている人、思想を持っている人、作っているものを持っている人が集まってきて、やんちゃなクラスみたいな、統制が取れないクラスみたいな状態が理想なんじゃないかなと思っています。大学ってあんまりそうならないじゃないですか。同じことを学んでいる人と同じ所得階層の人で集まってしまう。どうやっても。みんなちゃんと授業聞いているか、後ろの方で喋っている人がいて、みたいな構図になるんですけど、もっと自由でいいはずで、小学校の時が自由だったじゃないですか、そういう場をもう一度Creative-LAB.として作れないかなと思っています。

髙野: そういう場所でありつつ、お互いのリスペクトがちゃんとある、というのが、作りたい状態ですね。そういう背景があって、「クリエイティブ」と言っているんですよね。つまり、クリエイティブって何やねんって感じなんだけど、あえて広く取る。一応、建築、デザイン、アートということを言っているんですが、広く取ることでそういう人が混ざり合ったらいいなと思っていて。ASIBAの運営チームは結構建築系のバックグラウンドが多いという意味では同質性が高くて、ちょっとまずいなと思っているんですが、ASIBAのプログラム参加者自体は最近多様性が増しているなという感じですね。
「飯を食わない」から始める
髙野: 次に、飯が食えることと魂を売らないこと、これを両立させるのが非常に難しいでしょう、というステートメントがあります。プログラム設計のコンセプトとして、やりたいことをやりながらお金を稼ぎ、でも軸はぶらさなかったりビジョンをちゃんと持ち続ける、というのは理想なんだけど現実的には難しいと。それをどういう風に保っていますか?あるいは保つには何が必要なんだろう?
森原: 飯を食わないのが最初だと思います(笑)。それは大事なことだと思っていて、飯が食えるが先にきて、やれることだけをやります、したいことができることだけをやります、となってしまうと、どうしても「飯が食える感」で、生存的欲求が満たされていく。だんだん生存本能みたいなものが消えていくわけですよ。なので、飯を食えないという状態でチャレンジしているということを肯定、自分で肯定してあげてほしいなと。それはすごく良いチャレンジしていると思っていて。いや、まだ全然スキルもないけど、私はこういうことを仕事にしたいし、こういう仕事しか受けないし、こういうものを作りたいから生きているんです、と。そこにだんだん、そのスタンスを明確にしながら小さい仕事で受けていったら、だんだん食えるようになってくるわけです。まず自己定義する。自分は何をする人、何屋さんなのか、どういうやつなのかという自己定義をして、初めは飯が食えないけどだんだん食えるようになってくる。私はそれを2年ぐらいやったんですけど、2年経てば食えるようになります。そこをスタンス取れるかどうかが、割とこう耐えられるかどうか、ということではあるなと思いますね。ただ、飯が食えないのは良くないので、最低限食えるようにしておくことは、どうにかして、社会の仕組みとしてもですし、自分の中でもやらないといけないなとは思っています。だから「魂を売る仕事はしない」ということでクリエイティブな純度を保っていくのが大事です。

須藤: 難しいですね。自分はもしかしたらエンジニア気質が強いので、エンジニアとかってある種スキルで食べられるというか、ちゃんと勉強したらそれなりに食い扶持はある、という。だからセーフティネットが森原よりはある気がしていて、そういう意味ではだからこそ挑戦できるというのはありますね。
髙野: そうだよね。それ僕とめっちゃ近いですよ。
須藤: ああ、そうかも。そうかも。さっきの話と繋がると、自信みたいなのはもしかしたらそっちにもあるかも。社会を変えられる自信があるからめっちゃ作りたい、というのもあるし、死なない自信があるからまだ頑張れる、という。
髙野: そういう自信みたいなものは森原さんもきっとあったでしょうね。
森原: あ、でも代替可能性が高いなと思いますよ、自分自身。なんていうか、その当時も今もそう。割と自分が何もできない存在だと思ってますね。だからこそめちゃ仕事しなきゃ、と思ったりとか、色々なもの作ってみなきゃとか、止まってる暇ないわ、というのが多分構造的にインプットされてしまっている気がしてて。
高野: それは意外です。東大生が一番代替可能性の権化みたいな感じなんですが(笑)。
森原: そんなことないです(笑)
髙野: それこそ「クリエイティブ」って言った時の特別な響きって、代替可能性がないことに依拠してる部分が半分ぐらいあるんじゃないかな。僕は結構オペレーショナルに手を動かしていても飽きないし、それをなんか続けられちゃうタイプなので、むしろめちゃくちゃ代替可能性あるなと思いながら、どうしようかなと(笑)。でもなんか代替可能でもいいんじゃないかなって、最近思っていて。それが社会的な価値にちゃんと跳ね返ってるって自分で思えてれば、別にそれで幸せだなって思うので。そもそも、そうやってやっていった先にしか代替可能性はないわけですし。
森原: そうだよね。生まれない。めちゃくちゃそうだと思っています。やると自分が相対化されて、どういうものを作りたいのかなとか、が分かると思うんですよね。自分の中で温めていてもそれ出てこなくて、なんか世に出してみたりとか、ちょっと安全地帯を抜けてみた時にようやく相対化されてアイデンティティが分かる、というのはあると思いますね。
Related Articles
プログラムレポート
DAY7 PROJECTS FAIR / TSG Creative-LAB.|ASIBA
プログラムレポート
DAY6 + Open TALK #4 「つくること」と「生きること」の重ね方とは? / TSG Creative-LAB.|ASIBA
プログラムレポート
DAY5 + Open TALK3 日常/非日常の往復と、クリエイションの視座 / TSG Creative-LAB.|ASIBA
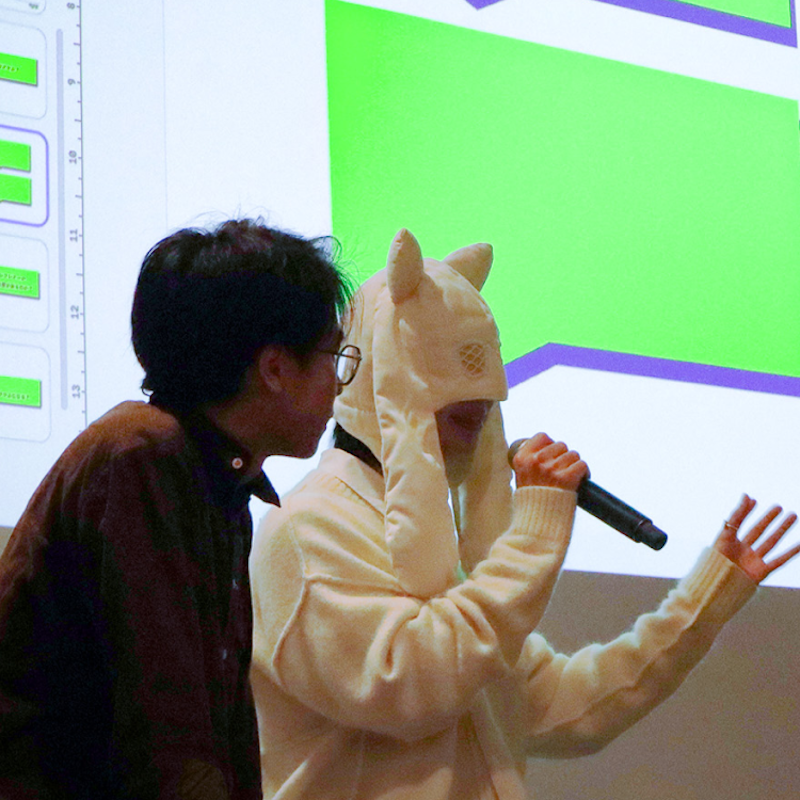
プログラムレポート
DAY7 PROJECTS FAIR / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート
DAY6 + Open TALK #4 「つくること」と「生きること」の重ね方とは? / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート